書物のデジタル化
*
私は読んだ本をデジタル化していますが、読んでいない本はしていません。
本は読むもの、知識を得るものです。
昔は百科事典(学研百科事典、某社のホーム百科事典)も全部通読していました。
*
本を読まずにデジタル化して、iPad に入れて必要なときだけそれを検索する人がいますが、そうすると本の内容は大部分が死蔵になってしまいます。
実にもったいないことです。
ここからは読影医としての読書の話になりますが・・・
読影医は OJT(on the job training)として、自分の経験した症例だけをマスターしていけばいいという意見の方もおられるかもしれませんが、読影のための知識の体系が身についていないと、個々の知識も自分の血肉になりません。
教科書を読んで体系を一度身にまとい、それに自分の経験した症例を付け加えていくのが王道です。
自分の経験した症例しか所見をつけられない人に限って、「私の経験では・・・」とかよく口にするのですが、読影医歴25年以上になる私から見ると「百年早い」と思います。私はおこがましくてそういう言い方はとてもできません。
*
大学院にいたころ、「これからはコンピュータで検索したらすべて出てくるようになるので、細かいことは覚えなくてよくなる」、と言っていた読影医もいましたが、たいていのことは知っておかないと、いちいち調べながらでは一日100件の所見はつけられませんね。せいぜい20件どまりでしょう。
一日100件(ふだんの 5倍ということです)所見をつけて、20年ほど読影したら、5×20で 「百年早い」 とは言われなくなります、たぶん。
###
関連記事
-

-
「画像診断クラウド研究会 in OSAKA 2013」のご案内
* お知らせです。 2013年2月2日、「画像診断クラウド研究会 in Osaka 2013
-

-
PET/CT検査の保険適応について
平成22年4月より、PET/CT(ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影)の適用疾患が変
-

-
イーサイトに似たクラウド型遠隔画像診断システム
* 世の中、物わかりの悪い人や文句ばかり言っている人がいないと、改善されません。 世界は
-

-
読影レポートの重要性 / CT,MRI を有する単科のクリニックの場合(2)
前回の記事「読影レポートの重要性 / CT,MRI を有する単科のクリニックの場合」 の続きです
-

-
spared lesion は間違い
* 脂肪肝で、周囲より脂肪浸潤の少ない領域が見られることがあります。 血管支配によることが多
-

-
4列マルチスライスCTが安い!
未確認情報ですが、風の噂でどこかの病院が 4列マルチスライスCTを 1600万円
-

-
視床は基底核ではありません
諸説あれど、一般的には・・・ 狭義の大脳基底核=被殻、尾状核、淡蒼球 広義の大脳基底核=
-
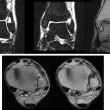
-
関節のMRIは GE(FE)が基本
最近のMRIで関節(膝・肘・肩・股・手・足)の撮像のとき、やたらめったら 脂肪抑制T2WI FSE
-

-
獣医師のための遠隔画像診断
今日のオンラインニュースを見ていたら、獣医のための遠隔画像診断プロバイダがすでにあるようですね。











